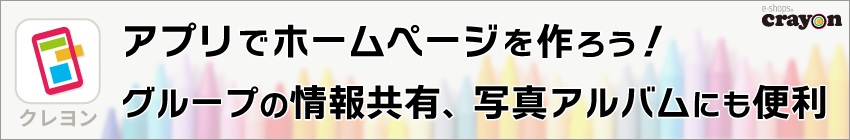「自由」 ポール・エリュアール
2024.5.25(山口修)
「自由」
ぼくの生徒の日の ノートに
ぼくの机に 樹々に
砂に 雪に
ぼくは書く おまえの名を
読まれた すべての頁に
空白の すべての頁に
石 血 紙 灰に
ぼくは書く おまえの名を
金塗りの 聖像に
戦士たちの 武器に
王たちの 冠に
ぼくは書く おまえの名を
密林と 砂漠に
巣に えにしだに
ぼくの幼年の こだまに
ぼくは書く おまえの名を
夜々の 不思議なことに
日々の 白いパンに
婚約の 季節に
ぼくは書く おまえの名を
青空の すべてのぼくの襤褸(ぼろ)に
池の 黴びた太陽に
湖の 生きている月に
ぼくは書く おまえの名を
畑に 地平線に
鳥たちの 翼に
そして 日陰の 風車に
ぼくは書く おまえの名を
曙の 閃きごとに
海に 船に
狂った 山に
ぼくは書く おまえの名を
雲の 泡立ちに
嵐の 汗に
重苦しい 気ぬけの雨に
ぼくは書く おまえの名を
きらめく 形態に
色とりどりの 鐘に
物理上の 真理に
ぼくは書く おまえの名を
めざめた 小道に
ひろがった 道路に
溢れる 広場に
ぼくは書く おまえの名を
ともる ラムプに
消える ラムプに
集った ぼくの家族に
ぼくは書く おまえの名を
鏡と ぼくの部屋の
二つに切られた 果物に
空(から)の貝殻 ぼくの寝床に
ぼくは書く おまえの名を
食いしんぼうで やさしい ぼくの犬に
その立てた 耳に
その不器用な 足に
ぼくは書く おまえの名を
バネつきの ぼくの戸に
親しみふかいものの 数々に
祝福された炎の 波に
ぼくは書く おまえの名を
調和のある すべての肉体に
ぼくの友人たちの 額に
差しのべられる手の それぞれに
ぼくは書く おまえの名を
驚きの 窓に
待ちうける 唇に
沈黙を はるかに超えて
ぼくは書く おまえの名を
こわされた ぼくの隠れ家に
くずれた ぼくの燈台に
ぼくの倦怠の 壁に
ぼくは書く おまえの名を
欲求のない 放心に
裸の 孤独に
死の 歩みに
ぼくは書く おまえの名を
もどった健康に
消え去った 危険に
想い出のない 希望に
ぼくは書く おまえの名を
そして ただ一語のちからで
ぼくは ぼくの人生をふたたび始める
ぼくは生れた おまえを知るために
おまえを 名づけるために
自由よ。
〈木島 始訳〉
(世界反戦詩集』(1970年 太平出版社)より引用)
1.静かな圧倒
この詩を読むたび何かに圧倒され続けてきました。それは、喉元を熱くさせるような静かな圧倒と言えばいいでしょうか。幾度も読んできたこの詩の内容も結末への展開も知り尽くしているにも拘らず、何が私を圧倒するのでしょう。それがいったい何であるのかを今回初めて考えてみようと、久しぶりに朗読してみました。
2.作者と「自由」
ポール・エリュアール(1895-1952)は19世紀末、パリ郊外のサンドニに生まれました。祖国と人民を愛した詩人であり、それら愛したものたちの自由と尊厳を守るために書いた作品の中のひとつが「自由」です。第二次世界大戦時、フランスがナチスドイツに占領されている最中にこの「自由」は生み出され、街中に貼られ、口々に囁かれ、瞬く間に人々の間に広まりました。抵抗の精神を奮い立たせ、屈することなく祖国解放を目指すための大きな役割を果たしたのです。「自由」は所謂レジスタンス詩の中においても特に知られた一篇といえるでしょう。
この作品は当初、愛する女性に捧げられるはずでした。最後の呼びかけは“自由よ”ではなく、その女性の名だったわけです。確かに最終行に、その当時愛していた女性の名前(妻であったヌーシュ)がきても、恋愛詩として多くの人の記憶に残る作品になったことでしょう。でもそれは突き抜けてはいても限定された、ある範疇に収まる詩になっていたかもしれません。“その当時”愛していた女性、ということですから。読む人に愛の普遍的情感を想起させるに十分な作品だとしても、この詩を自由に捧げ、自由を渇望する同胞に届けるよりは見劣りしてしまう気がしてなりません。
ポール・エリュアールは詩を書き始めて間もなく、19歳で第一次世界大戦に召集され戦地の非常さの極みを目の当たりにします。その後、ダダイスムを経て、シュールレアリスムの運動に参加。アラゴンとともに、ブルトン、デ・キリコ、エルンストらとシュールレアリストとして活動する中で平和反戦運動に身を投じ、さらに共産主義へ傾倒していきます。政治的、思想的な立場を共にした仲間との協働、そして時に離反もある中で、一貫していたのは祖国フランスとその人民への深い愛を持ち続けたことです。生活を脅かされ自由が奪われることに対し戦い抵抗することを諦めず、それが詩作品に投影されたとき、分け隔てない人間への愛へと昇華するのは必然的なことでした。
3.“書く”
この詩は、タイトルと本篇最終行に登場する“自由(よ)”に挟まれた4行1連×21連で構成されています。第21連を除き各連の4行目にはすべて〈ぼくは書く おまえの名を〉が置かれ、この詩を初めて読む人でも、(おまえ=タイトルワード=自由)であるとほぼ推測して読み進めることになります。かたちある物、所有物、抽象的事物、それらここに列挙したものに“書く”というのです。
名を書く、と言われれば、例えば子供の持ち物に名前を書き入れたり、宛名、差出人として手紙や書類に氏名を記入することを思い浮かべるのが普通です。第3連までは実際に“書く(書きこむ)”ことのできるものとそうでないものが混在しますが、第4連以降はほぼ書きこむことのできないものが並びます。不思議です。こうして“書く”という言葉の表す実際の意味を追いかけると、どうも腑に落ちない文章になるのに、詩の一節として読むとなんら〈ぼくは書く おまえの名を〉に疑問を持ち得ない。自然とこの1行が体に入ってくる。“書く”という行為が、読む側の頭で即座に別の何かに変換されているのでしょう。ノート、頁、冠 等々、意味の通る第1連から2連3連と進む僅か12行で、この詩の流れに乗せられているともいえそうです。
詩人は詩を書きます。PCやスマホでも詩作できる現在と違い、エリュアールの生きた時代においては、広げた紙を前にペンを走らせる以外に、詩を書く姿を想像することはできません。言葉がかつてないほど軽んじられている、と言われる昨今ですが、一方、その言葉を“書く”という行為の担う目的が、エリュアールの時代と比べて変わることなく紙面や液晶画面上に果たされているか大いに疑問です。書くことが廃れていないか。書くという行為がいずれ消え去ってしまう、今すでにその過程に踏み込んでいるのでは、という考えも否定できません。文字を、言葉を書くことは必要だと言い切れるのか、人間はまだ“書くこと”の意味と対等でいられる何かを持ち続けているのか、、、即答できません。100年前の、特に詩人の内には “言葉”と“書く”との間に、お互いがお互いを必要とする密で尊い繋がりが、ごく自然なかたちで在ったのではないでしょうか。“書く”という人間独自の行為が、手さきだけに限らず彼の肉体表現として大切に愛おしく染み込んでいた。だからこそ概念である“自由”を“書く”という動詞によって人間の世界に再び生かしめ、その実をひとりひとりの日々の中に結ばせようとしたのではないでしょうか。
4.省くことなくすべてを
各連のほとんどは、程度の差こそあれそれぞれの連ごとにその内容に関連性を持っていて、身の回りのもの、自然(現象)、身体の部位等々、お互い近しい関係にあるものであり、関連付けを容易に想像できるもので構成されています。
エリュアールはすべてを言い尽くしました。そうしなければならなかったのです。生活と人生のすべてを言い尽くす。どれか一つでも欠いては、(ぼくの)自由は成り立たない、すべてが存在しなくてはならない、そこに当たり前に在るものとして必要だ、と。そのどれも取りこぼさずに一つ一つこの詩へ捧げるように書き記す。その総体によってでしか自由に釣りあい得るものはない。この今自由であるためにそれらすべてに“おまえの名”を記さなくてはならない、、、ピンと立てた犬の耳、そしてその不器用な足にまで。
「削りなさい」、詩を書く時にとにかく削ることを私自身ずっと言われてきました。もちろん無駄な言葉を削るということです。詩で語るよりは、語らない部分で何を伝えられるか。省かずすべてを言うことで完成に至るこの作品は、その意味でも稀有な存在です。
しかも、一語か二語、多くて三語から成る平易な言葉の組み合わせによる名詞(句)で描写されたものたちは、読み手の想像力を少しも縛らずに、字数と反比例するように最大限にイメージを広げることに寄与しています。木島訳に負うている、語句選択による単純で簡潔な確かさがこの翻訳詩の肝であり支えでもあります。夜々の不思議なこと、驚きの窓、待ちうける唇、池の黴びた太陽、湖の生きている月、嵐の汗、めざめた小道、想い出のない希望、裸の孤独、、、なんと広がりある豊かなイメージを放っていることでしょう。世界にはここに書き記されたものだけあればいい、と思えるくらいに!
抵抗詩の代表的な書き手として、アラゴンとともにエリュアールを紹介した加藤周一氏も、原詩を読み自ら翻訳しつつこう書き記しています。「童謡のように単純な形式と、日常的な単語。しかしなんという感動がそこには脈打っていることであろう」(加藤周一『小さな花』(2003年 かもがわ出版)より引用)。
5.翻訳詩として読む ―木島始の日本語訳―
〈ぼくの生徒の日の ノートに〉から、一連一連を読み進めてゆく程に、平明で高ぶりのないこの詩の語り口とは対照的に、黙読の無音の声の中にさえ熱が帯びてくるのを禁じ得ません。静かに圧倒されるほどにこの詩を読ませるもの、この詩が内包し一向に減ずることがないものがあるのです。20連に並べられた、詩人の内部、外部の世界を凝縮し表出させたものたちの描写の秀逸さはもちろんのこと、自由を語るにはそれらすべてを言い尽くすしかないという衝動のようなものが、読む毎回ごと新たに、4行1連の流れの中に溢れるように途切れることなく伝わります。
黙読にしても朗読にしてもこの詩はどう読まれるのが相応しいのでしょうか。初めから終わりまで淡々と唇にのせればよいのか、それとも一連、一行ごとの語句の内容を汲んで、その語気に考慮した読み方をするのがよいのか。フランス語で読む場合と日本語で読む場合とで、その言語的構造がもたらす何かしらの相違が生じることもあるのかもしれません。
フランス語による朗読の一つを聴いたところ、連によりかなり抑揚に変化をつけていた印象でした。和訳では調子はほぼ一定、抑揚は抑え気味の朗読が合うのではないかと個人的には考えます。言語に関係ない部分では、4行連詩の視覚的明瞭さ、読むうえでの呼吸のつかみ易さなどの点も、この詩をより親しみやすくする要因として挙げてよいでしょう。とは言っても、読む人それぞれが自分のリズムを獲得してゆく4行21連であっていいのです。
読むという行為は言葉を発すると同時に聴いています。自らの声に耳を傾けるまでもなく、いつの間にか詩が内なる声で直接語りかけはじめるとき、躯体に伝わる言霊を直観することができるように感じます。そんなとき、詩との一体感を得るのです。
ポール・エリュアールによる「自由」を木島始訳で最初に読んだこと、まったくの偶然でした。他の訳者の翻訳によるものも幾つか読みましたが、どうしても木島訳のように心が動きません。名詞の羅列といってもいい作品ですから、訳者により若干の言葉選びの違いはありますが、詩の内容は変わりません。20連にうたわれた数々のものたちはどれも単純明快で飾り気のないものごとです。使われた形容詞は、日本語訳において、白い、重苦しい、やさしい、親しみふかい、これら4つを数えるだけです。私にとっての木島訳は、選ばれた一つの言葉、また組み合わされた言葉と言葉の力が豊かなニュアンスを含みながら、一番大きく発揮されているということでしょうか。
顕著な違いが一つ、木島訳を際立たせています。ほとんどの日本語翻訳詩には例えば第16連であれば、〈調和のある すべての肉体の上に/ぼくの友人たちの 額の上に/差しのべられる手の それぞれの上に/ぼくは書く おまえの名を〉といったように、名を書く場所としての名詞句に続けて、そのほぼすべてに“~の上に”が付きます。これはフランス語原詩にある前置詞”sur(上に)”を受けての、ある意味直訳で正しい訳です。原詩では各連4行目にあたる〈ぼくは書く おまえの名を〉の前3行の各文頭に、いくつかの例外はあるものの”sur”が置かれています。しかし木島訳はただの一度も“~の上に”を用いていません。ある意味正確さを欠いているとも言えます。ただし木島訳は、だからよいのです。“~の上に”をすべて省いた「自由」は、読み手が詩行から受け取ると同時にイメージを存分に解き放つための最大の配慮をしている、と言ってもよいのではないか、もちろんこの点には異なる意見もあると思います。
繰り返しになりますが、すべてを言い尽くした詩であるのにもかかわらず、削ぎ落とされた個々の言葉が単純さを極めた結果、作品そのものが堅固で過不足なく充足していること。この詩の特質の一つに数えてよいのではないでしょうか。
6.抵抗という希望
抵抗するという前向きの意志、そこにわずかでも望みがあってはじめてエリュアールの握るペンが書かせた作品ではないか、一片の希望も持ち得ない絶望に包まれた人にはこの詩はうたえないのではないでしょうか。現在、世界は悍ましい日常が当たり前の毎日となり、家を破壊され、家族を殺され、故郷を追われ、生きていることさえ苦しみと悲しみしか生み出さないような場所があります。今生きるだけの命に精いっぱいで、“日々”と呼べるものが全く失われた場所です。虐殺者にこの詩が届かないように、家族の、そして自らの命が、虐殺者の手にすでに握られている人々へも、この詩を届ける術を失っているかのようです。
しかし、他人の絶望を目の前にした人間は他人の絶望に絶望してよいのでしょうか。今日、今のところ殺されることのないだろう人間が持ち得るもの、抵抗の希望こそがそれではないでしょうか。そのことを考え続けるため、この一篇があり、この一篇の詩を読む。絶望に絶望で応えないために。
7.最後に
ポール・エリュアールの「自由」を紹介しながら、読む度に覚える感動の源を考えてみました。詩人に強く影響を及ぼしたダダイスムからシュールレアリスム、共産主義への関わりなどの側面から作品を捉えるまでには至っておらず、よってこの詩のある一面を拾い上げたに過ぎません。ただ、今後もこの感動を持ち続けることができるなら、その感動を一人ささやかでも抵抗の心にかえていくこともできるはずです。それは、なんでもないありふれた日常を、日々と呼べるあたりまえの毎日を破壊するもの、奪おうとするものへの抵抗の力です。
エリュアールは自分を鼓舞するように最後にこう綴りました。
〈そして ただ一語のちからで/ぼくは ぼくの人生をふたたび始める〉
この言葉が絶望の暗闇にいる人の唇に伝わり、いつかその人自身の声として発せられることを願います。
―参考文献―
飯島耕一『現代詩が若かったころ ― シュールレアリスムの詩人たち』1994年
© Osamu Yamaguchi 山口 修
▼アーカイブ▼
- Link
- blog
- Twitter
- こちらのパーツは項目ごとにリンク設定が可能です。